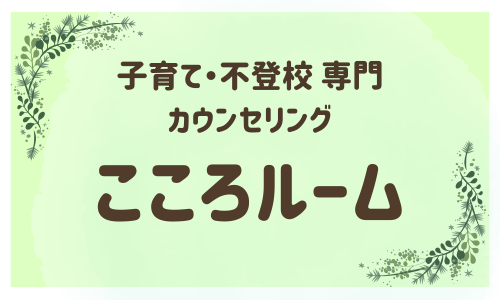登校しぶりから不登校にさせないために大切なこととは

小学校1年生が入学してしばらくすると、朝、昇降口でお母さんにしがみついて泣く子どもの姿が毎年のように見られます。
そして近年では、学年が上がっても同じように泣いている子どもや、毎日のように家で泣いてから登校する、いわゆる「登校しぶり」の子どももよく見られるようになりました。
登校しぶりの原因とは
登校しぶりの原因で最も大きなものは、母子分離不安です。
母子分離不安とは、母親と離れる際に、その年齢にはそぐわないほどの強い不安や恐怖をもつ状態のことを言います。
1歳の子どもが母親と引き離されると不安で泣くのは当たり前のことですが、それが学童期に入っても続くような場合は、その子に母子分離不安があると考えられます。
母子分離不安になる原因
1歳の子どもは母親と離れて遊んでいても、すぐに振り返って母親のもとに抱きついてきます。
そして、しばらく抱きついた後にまた離れて遊び始めます。
この場合、母親が自分の近くにいること、駆け寄ると抱きしめてくれることが子どもの心の安全基地となります。
これを繰り返すことにより、母親から離れても安心であるということを学び、離れることへの不安が徐々に減っていきます。
そして、年齢が上がるにつれ、より長い時間、より遠くでも、母親と離れて過ごすことができるようになってくるのです。
母子分離不安になる子どもは、この過程で母親を安全基地として認識することができなかった子どもです。
例えば、
・母親と常に一緒にいて、離れて遊ぶことが少なかった。
・離れて遊んでいても、母親がすぐに寄ってくることが多かった。
・離れて遊んだ際に、振り返って母親がいないことが多かった。
・駆け寄っても抱きしめられることが少なかった。
このような経験があった場合、年齢相応の母子分離ができずに、母子分離不安になってしまうのです。
母親側の母子分離不安
母子分離不安は、子ども側だけの問題ではありません。多くの母親にも分離不安が見られます。
母親はいつも、子育てについて多くの不安を抱えています。
特に近年は、子育ての「正解」についての情報があふれかえっており、母親は常に「正解」のプレッシャーにさらされています。
また昔に比べ、少しのことでも批判の対象となりやすい時代になり、子育てに対するハードルも上がっています。
そのため、
・子どもにとってこの環境はよくないのではないかと、先回りして環境を変えてしまう。
・子どもが自分から離れると、心配ですぐに近づいてしまう。
・他の子と遊んでいると、嫌なことをされていないか、していないか、楽しく遊んでいるかなどが気になってしまい口を出してしまう。
など、母親が子から離れることができない状態になりやすいのです。
不登校は登校しぶりの延長上にある
「登校しぶりが突然始まった」と感じる親は多いですが、実はこのような乳幼児期からの母子関係の延長上に登校しぶりはあります。
小学校生活はそれまでとは大きく違い、子どもの自立が試される場です。
母親と離れる練習を上手にやってくることができなかった子どもは、小学校入学などの大きな環境変化に耐えることができず、朝、母親と離れることを恐れるようになります。これが登校しぶりです。
このことを知らずに、無理やり引っ張って登校させるなどをすると、子どもは心の安全基地が無いまま学校生活を送ることになってしまいます。
このような不安定な状態の心をもった子どもは、トラブルなどが起きた時に上手く回避したり乗り切ったりすることができません。
そして、トラブルなどで感じた不安が消化されることなく心の中に積もっていき、これ以上抱えきれなくなった時に学校に行けなくなってしまうのです。
不登校もまた、突然始まったように見えますが、実はこのような積み重ねの上にあるのです。
不登校を防ぐためには
登校しぶりから不登校になるのを防ぐためには、なるべく早い段階で母子関係の見直しを行うことが重要です。
つまり、子どもが「お母さんは安全基地なんだ」と認識できるようにしていくのです。
それは、幼少期に上手くできなかった母子分離のやり直しをするということでもあります。
母親と少し離れる
→振り返ると母親が見守っている
→駆け寄ると抱きしめてくれる(受け入れてくれる)
→昨日より少し遠くへ、長い時間母親と離れる
このよう、小さい頃に上手くできなかった分離の過程をたどっていくことで、母子分離を進めることができます。
それを繰り返すことで、母親と長く離れて自立が求められる場所に行っても、安心して過ごすことができるようになるのです。
母子関係の見直しはいつでもスタートできる
幼少期に母子分離が上手くできなかったといっても、遅すぎるということはありません。
このコラムを読んでいる時点で、もうすでに、あなたの母子関係の見直しは始まっています。
よりよい未来に向けてのスタートは、いつでもきることができるのです。