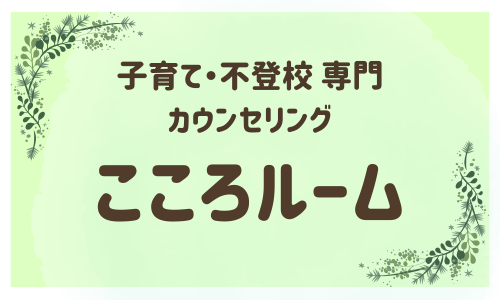不登校の子どもをもつ家庭に見られる共通点とは

不登校の子どもをもつ多くの家庭と出会ってきましたが、そこには多くの共通点がみられます。その一つが、お父さんの影があまり見られないということです。
面談に訪れたお母さんは、子どもの家での様子、辛い気持ち、自分と子どもとの関係性などたくさんの話をされますが、その中にお父さんの話題が上がってくることはあまりありません。こちらからあえて「お父さんは?」と質問するまで、ほとんどの場合触れることはありません。
不登校は家庭を揺るがす大問題です。それなのにそこにお父さんの影が見えてこないのはなぜなのでしょうか。
不登校の家庭に共通するお父さんの姿とは
お母さんへの質問の中からやっと見えてきたお父さんの姿にも、驚くほどの共通点があります。
・不登校についてあまり深く考えていない、また自分の考えを押し付ける
・子どもの様子や変化に気付かない、わかってない
・頼まれたらするが、自分から不登校解消に向けて行動しない
・生活リズムや働き方は子どもが不登校になる前とあまり変わらない
これらのお父さんの姿は、相談に訪れるほど悩んでいるお母さんの姿とはあまりに違います。
しかし、不登校の子どもがいる家庭の中では、これが一般的なお父さんの姿なのです。
不登校の子どもがいる家庭だけの話ではない
なぜ不登校の子どもがいる家庭のお父さんには、このような共通点が見られるのでしょうか。
理由として考えられる1つとしては、子育てで父さんの姿が見えないというのは不登校の子どもがいる家庭に限った話ではないといことです。
例えば学校の懇談会、PTAなどを見てみてください。そこでのお母さん・お父さんの比率はどれくらいでしょうか。私立、公立など学校の風土、地域差はもちろんあると思いますが、多くの場合8:2といったところではないでしょうか。
私の経験上ではもっと偏っており、9:1ぐらいの割合でお母さんが参加していました。また、会によってはお父さんが一人もいない場合も少なくありませんでした。
子どもの提出物の管理はどうでしょう。学校からのプリントやメールを把握して、準備するものを整えているのはお母さん、お父さん、どちらでしょうか。
子どもが風邪をひいた場合に学校に連絡を入れるのはどちらでしょう。また反対に学校で発熱した場合に最初に連絡が来るようにしているのは誰の携帯電話でしょうか。
たったいくつかの例ですが、父母ともにいる家庭において、このすべてをお父さんが中心に担っている家庭は非常に珍しいと思われます。その一方ですべてをお母さんが中心に担っている家庭は大変多く、私も今まで数えきれないほど出会ってきました。
つまり、不登校に限らず、子どもに関わることの大半をお母さんが担っている家庭が、そもそも多いということなのです。
お父さんの子育てと子どもの不登校の関係
2つめに考えられる理由としては、お父さんが子育てに協力的でない家庭では、子どもが不登校になる条件が生まれやすいということです。
お父さんが協力的でないということは、そのままお母さんの負担が増えるということにつながります。負担といっても家事などの物理的なものだけではありません。子育てにおける「責任」がその一つです。
お母さんは常に「私がしないとこの子は・・・」という危機感をもって子育てをしています。
健康面など命と直結するものから、学校の提出物、宿題など細かなところまで、自分が責任をもって管理していかないと、子どもの健康や安全、楽しい生活が脅かされてしまうということを常に考えているからです。
だから、例え仕事が忙しくても、自分の体調が悪くても子どものご飯をつくったり宿題の心配をしたりするのです。まさに人生を削って子育てをしています。
一方、多くのお父さんはそうではありません。
子育てにおける第一の責任を背負っているのはお母さんであり、お父さんはそのサポートというポジションの家庭がとても多いです。
中にはそのサポートですら行わないお父さんもいます。
その場合、子育てにおけるお母さんの責任はさらに増し、心身への負担へと直結します。そしてお母さんの心身の疲れは、育てている子どもへと伝播し、不登校になる条件を生みやすくしているのです。
不登校解決への第一歩
昔に比べ、「父親の育休取得」「イクメン」など、お父さんの育児参加への一般的認知は広がってきていますが、当事者のお母さんにとってみれば、まだ微々たる変化でしかないのかもしれません。
特に子どもが不登校になってしまう家庭の多くでは、子育てにおいて夫婦間で比重が偏り、方向がばらばらになってしまっています。
子育ての「責任」を夫婦で共有し方向や比重を整えていくこと、それが不登校解決への第一歩につながっていきます。